









| Tweet |
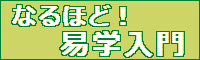 �����ł͈Պw���Ռo�i���Ձj�Ɋ�Â��肢�̐��藧���ɂ��āA���S�Ҍ����ɉ�����Ă��܂��B�Ղ̋N���͒����̗L�j�ȑO�A�܂��������Ȃ��������ゾ�ƌ����Ă��܂��B �����ł͈Պw���Ռo�i���Ձj�Ɋ�Â��肢�̐��藧���ɂ��āA���S�Ҍ����ɉ�����Ă��܂��B�Ղ̋N���͒����̗L�j�ȑO�A�܂��������Ȃ��������ゾ�ƌ����Ă��܂��B
���@�v�����[�O�@�T�@�Ղ̊�{�@�A�Ɨz�@�U�@�Ղ̎��Ӂ@�܍s�`���@�V�@���T�ƌĂ�钊�ی|�p�@���̂P�@�W�@���T�ƌĂ�钊�ی|�p�@���̂Q�@�X�@�Ղ̎���@�Z�\�l�T�@�Y�@�Z�\�l�T�Ɠ��{�����@�Z�@�Z�\�l�T�̏��������T�`�E��с@�[�@�Z�\�l�T�̏��������T�`�E�����@�\�@�j�����ڂƏ����j���@�]�@�肢�� �Z�@�Z�\�l�T�̏��������T�`�E����@�������̎q�̘b���ƁA���̒j�������͐g�����o���ĕ������Ƃ���B�������Ղ�̘b���ƁA�Ƃ���Ɏ��ʓ|�L�����Ȋ�t���ɂȂ�B����͌��ゾ����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�w �@�����ŁA���́u���T�`�v�̕��͂��Љ�A���������Z�\�l�T�e�T�̉���ɐG��Ă݂邱�Ƃɂ������B |
���T�`�@����P䷀ 13䷌ �̂ɂ������ɓ��l�������Ă��A�l�Ɠ���������҂͐l�]�����ɂ��đ����̕��K������� 14䷍ �̂ɂ������ɑ�L�������Ă��A���L����҂͂����ĉm��� 15䷎ �̂ɂ������Ɍ��������Ă��A���L���Ĕ\�������Ȃ�ΕK�� 16䷏ �̂ɂ������ɗ\�������Ă��A�\�т�҂ɂ͕K�� 17䷐ �̂ɂ������ɐ��������Ă��A��т݂̂ɂĐl�ɐ����҂͕K���������N�������Ƃ���A 18䷑ �̂ɂ����������������Ă��A���Ƃ͎����Ȃ�A��������ΗՋ@���ςɏ������Č�ɏ̎^��Ȃ�ׂ��A 19䷒ �̂ɂ������ɗՂ������Ă��A�ՂƂ͑�Ȃ�A����Ȃ�ΑR���� 20䷓ �̂ɂ������Ɋς������Ă��A�ς�ɒl���Č�ɑ��҂�������č�������A 21䷔ �̂ɂ������ɚ�嗑�������Ă��A嗑�Ƃ� 22 �̂ɂ��������ʂ������Ă��A�ʂƂ͏���Ȃ�A������ی��Ȃ��v���đR���� 23 �̂ɂ������ɔ��������Ă��A���Ƃ� 24 �̂ɂ������ɕ��������Ă��A������ 25 �̂ɂ������ɝٖς������Ă��A�ς� 26䷙ �̂ɂ������ɑ�{�������Ă��A���{���đR���ɗ{����Ă�ׂ��A 27䷚ �̂ɂ���������������Ă��A��Ƃ͗{���Ȃ�A�{�킸���ē����ׂ��炸�A�{���ē������͑傢�� 28䷛ �̂ɂ������ɑ�߂������Ă��A�������ĉ߂���ɏI���ׂ��炸�A�߂�����͖Ӑi����ĕK�� 29䷜ �̂ɂ������ɚ��������Ă��A���Ƃׂ͊�Ȃ�A�ׂ�ΕK�� 30䷝ �̂ɂ������ɗ��������Ă��A���Ƃ� ���@�Ȃ����T�̐����ł��G�ꂽ���A�Ղ������������́A���̎��́u�͂Ȃ��v�ł͂Ȃ��A�^�t�́u�t������v�Ƃ����Ӗ��Ŏg���Ă����B �ȏ�A��юO�\�T�B |
�ŏI�X�V���F�ߘa07�N11��09�� �w�L�u��
Copyright Heisei12th�`Reiwa7th�i2660�`2685�j�@�iC�j2000�`2025 GakuEki-UQkai
���T�C�g�̓��e�͂��ׂĖ��f�]�ڂ��֎~���܂�