









| Tweet |
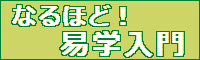 ここでは易学=易経(周易)に基づく占いの成り立ちについて、初心者向けに解説しています。易の起源は中国の有史以前、まだ文字がなかった時代だと言われています。 ここでは易学=易経(周易)に基づく占いの成り立ちについて、初心者向けに解説しています。易の起源は中国の有史以前、まだ文字がなかった時代だと言われています。
○ プロローグ Ⅰ 易の基本 陰と陽 Ⅱ 易の周辺 五行〜儒教 Ⅲ 八卦と呼ばれる抽象芸術 その1 Ⅳ 八卦と呼ばれる抽象芸術 その2 Ⅴ 易の主役 六十四卦 Ⅵ 六十四卦と日本文化 Ⅶ 六十四卦の序次=序卦伝・上篇 Ⅷ 六十四卦の序次=序卦伝・下篇 Ⅸ 男尊女卑と女尊男卑 Ⅹ 占い方 Ⅸ 男尊女卑と女尊男卑序卦伝に込められた女尊男卑への警戒心父と子の関係現代人にとっての文語体の文章は、堅苦しく読むのに骨が折れる。しかし敢えてここに取り上げた。何故なら、その処世術としての面白さや各卦の配列に注目したかったということもあるが、もう一つ、今後の社会を考えると実に興味深い箇所があったからである。下篇冒頭の次の文章である。
一見、儒教の価値観に従って当たり前のことを当たり前に書いているようでもあるが、注意深く読むといささか気になるのころがある。 モソ族の場合 まだ平成になったばかりの頃、中国政府の許可を得て産経新聞が中国雲南省奥地を取材した。 その少し前までのモソ族は、道なき道で険しい峠をいくつも越えたところにある |
母権制社会と父権制社会このモソ族ような社会形態は特殊な環境が生み出した異端だとする見方もあるが、古代中国ではかなり身近な存在だったからこそ、下篇冒頭の文章があるのだと言えよう。 男女が結婚して夫婦となることで初めて父と子の関係が生じ、父と子の関係があって初めて君臣や上下の序を整える礼儀すなわち儒教道徳は成立するといった意味だが、逆に言えば、儒教道徳を否定すると生まれてくる子の父親を特定することが無意味になり、父と子の関係は成立しなくなると共に、女性達は不特定多数の男性との性交を楽しむため、結婚という制度も崩壊すると示しているのである。 一般にモソ族のような社会は母権制社会、他の結婚という制度を有する社会は父権制社会と呼ばれているが、この両者を比較してみると、男女平等は幻想に過ぎず、人間社会は男尊女卑か女尊男卑の何れかでしかなく、それは社会が結婚をどのように位置付けるかで決まって来るのだと言えよう。そして多くの場合、人類はその太初より男女が夫婦という単位を構成する父権制社会だったと考えられているが、そこには大きな誤りがあったのである。 もっとも、母権制社会を窺わせる記述は、司馬遷の『史記』や『日本書紀』にはちゃんとある。 |
女系天皇についての議論 秋篠宮悠仁親王殿下ご誕生まで、よく、女系天皇という言葉を耳にすることがあった。これまで、皇位継承は男系で来たわけだが、現在の宮家では将来男系での皇位継承が難しくなる可能性があったので、その回避策として言われだした言葉である。 『古事記』『日本書紀』は、表面上、古代日本は有史以前から父権制父系社会であったかのように描いているが、それはウソだと断言できる。
ちなみにキリスト教国では、キリスト教がその男系相続の王様の役割を果たしている。例えば、ローマ法王は男性しかなれない、というシステムが、無言のうちに、男尊女卑を人々に植え付けているのである。しかし、キリスト教国であっても、国民のキリスト教への信仰が薄れると、やはり男尊女卑はぐらつく。例えば次のような事例がある。 男女平等が進むと・・・ もう十年以上前のことだが、ヨーロッパの女性についての興味深い記事が新聞に載っていた。 |
『旧約聖書』の場合 羞恥心と言えば、『旧約聖書』冒頭の「創世記」、そのアダムとイブのところに、こんなことが書いてある。 |










最終更新日:令和02年10月31日 学易有丘会
Copyright Heisei12th〜Reiwa2nd(2660〜2680) (C)2000〜2020 GakuEki-UQkai
当サイトの内容はすべて無断転載を禁止します