









| Tweet |
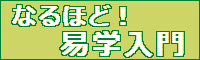 ここでは易学=易経(周易)に基づく占いの成り立ちについて、初心者向けに解説しています。易の起源は中国の有史以前、まだ文字がなかった時代だと言われています。 ここでは易学=易経(周易)に基づく占いの成り立ちについて、初心者向けに解説しています。易の起源は中国の有史以前、まだ文字がなかった時代だと言われています。
○ プロローグ Ⅰ 易の基本 陰と陽 Ⅱ 易の周辺 五行~儒教 Ⅲ 八卦と呼ばれる抽象芸術 その1 Ⅳ 八卦と呼ばれる抽象芸術 その2 Ⅴ 易の主役 六十四卦 Ⅵ 六十四卦と日本文化 Ⅶ 六十四卦の序次=序卦伝・上篇 Ⅷ 六十四卦の序次=序卦伝・下篇 Ⅸ 男尊女卑と女尊男卑 Ⅹ 占い方 Ⅱ 易の周辺 五行~儒教(1) 五行(木火土金水)と六十干支五行と相生相剋 よく陰陽五行という言葉を耳にするが、陰陽の基数の二と三を足すと五になるように、陰陽と五行の間には密接なつながりがあるから、こう呼ぶのである。
相剋それぞれの意味は、 ということである。 いろいろな事象への五行の配当 この相生相剋関係の説明は、いささか強引な感もあるが、古来そう言われているので、当面これに従っておくことにし、その五行に配される事象をいくつか拾ってみよう。 このほか、味覚では木を酸(すっぱい)、火を苦(にがい)、土を甘(あまい)、金を辛(からい)、水を鹹(しおからい)としてこれを五味と言い、徳目では木を仁(思いやりや博愛)、火を礼(礼節)、土を智(学問)、金を義(正義)、水を信(信頼)として、これを五常と言うのを始め、五行は種々の事象に配され、その調和が求められていて、戦争や災害などは、その調和が乱れるために起こるのだ、と考えらいている。 五行~十干十二支~六十干支 さて、そんな五行だが、それぞれを兄弟をもって陽と陰に分けると、次のような計十種の要素となる。 |
(2) 儒教とその誤解 儒教と言うと、長幼の序を重んじる堅苦しい道徳律としての印象が強いが、実際に中を覗いてみると、「仁」すなわち博愛慈愛、もっと簡単に表現すれば「思いやり」に満ち溢れた世の中を構築するための学問的仮説が展開しているに過ぎないのである。 当サイトでは、漢文で楽しむ論語というページを作った。横書き用の返り点を工夫し、『論語』全文を初心者でも漢文で読めるように作ったページです。もちろん書き下し文と現代語訳も添えてあります。 とにかく、この孔子が人間の生き方、理想的な社会の在り方を考えた根底にあるものこそ、易の理論なのである。論語には表面上そんなことは書かれていないが、それは 企業経営でいうと・・・ 上の者が下の者を思いやれば、下の者は親孝行をするように、上の者を敬い孝を尽くす。会社で言えば経営者が従業員の幸福を最優先に考え、常に理性的な経営を行えば、従業員としても経営者を尊敬し、喜んで頭も下げ、辛い仕事でも率先して頑張るようになり、その結果として業績は伸び、給料も上がり、社運は隆盛となる。 孔子が書いた唯一の本が『易経』なのだ! ところで、『論語』は孔子とその弟子たちの言行録を、孔子の弟子が書いたものであって、孔子が自分で書いたわけではない。またいわゆる ただ、現代のアカデミズムや出版界では、論語や孔子を紹介するとき、敢えて易との関係に触れないようにしていることが大多数である。恰も易を卑下しているかのように。 |
孔子と釈迦やキリストとの違い ところで儒教の祖と言われる |
結婚式に見るキリスト教式と神式の違い これらの点については、キリスト教と対比してみるとわかりやすい。 儒教がこのように宗教と一定の距離を置けるのは、人生の指針としては易がある上に、家族の絆を大切にしていれば、生涯孤独感に苛まれることはないと考えるからだ。逆に言えば、家族や先祖との関係を断ち切り、人生の指針を失えば、人は孤独と迷いの中で、死の恐怖に怯え、宗教の門を叩く、ということである。 |










最終更新日:令和02年11月04日 学易有丘会
Copyright Heisei12th~Reiwa2nd(2660~2680) (C)2000~2020 GakuEki-UQkai
当サイトの内容はすべて無断転載を禁止します