









| Tweet |
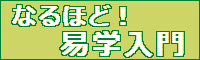 �����ł͈Պw���Ռo�i���Ձj�Ɋ�Â��肢�̐��藧���ɂ��āA���S�Ҍ����ɉ�����Ă��܂��B�Ղ̋N���͒����̗L�j�ȑO�A�܂��������Ȃ��������ゾ�ƌ����Ă��܂��B �����ł͈Պw���Ռo�i���Ձj�Ɋ�Â��肢�̐��藧���ɂ��āA���S�Ҍ����ɉ�����Ă��܂��B�Ղ̋N���͒����̗L�j�ȑO�A�܂��������Ȃ��������ゾ�ƌ����Ă��܂��B
���@�v�����[�O�@�T�@�Ղ̊�{�@�A�Ɨz�@�U�@�Ղ̎��Ӂ@�܍s�`���@�V�@���T�ƌĂ�钊�ی|�p�@���̂P�@�W�@���T�ƌĂ�钊�ی|�p�@���̂Q�@�X�@�Ղ̎���@�Z�\�l�T�@�Y�@�Z�\�l�T�Ɠ��{�����@�Z�@�Z�\�l�T�̏��������T�`�E����@�[�@�Z�\�l�T�̏��������T�`�E�����@�\�@�j�����ڂƏ����j���@�]�@�肢�� �V�@���T�ƌĂ�钊�ی|�p�@���̂Q�@���T�ƏW�������@�w�Ռo�x�́u�q����`�v�Ƃ����Ƃ���Ɂu�Ղ������L��A�������V���A���V���l�����A�l�ۂ����T���v�Ƃ������͂�����B�����Ȃ�Δ��T�͓�i�@�ɂ��W���������O��J��Ԃ����ƂŔ��������Əq�ׂĂ���̂��B
�@�R���s���[�^�����ꂽ�_�@�ɂȂ������w�̓�i�@��W���́A�I舂ɂ��ߑ�ȍ~�̗��_���Ǝv������ł����̂ŁA���̔��T�����ߒ��ɂ͈�u�ڂ��^�����B���������ׂĂ݂�Ƃ��̋ߑ㐔�w�ɑ傫�ȉe�����y�ڂ������̂������u�Ձv�������̂��B �@�u�ꂩ�����v�̓��`��́u |
�@��ɐ}�̐��藧��
�@�܂��~����N�ɋ[���A�~������Ď��A�Ď�����~���̓�ɕ�����B����Ƈ@�̂悤�ɁA�~���̒��ォ��Ď��܂ł̉~�̍������z�A�Ď��̒��ォ��~���܂ł̉~�̉E�����A�ƂȂ�B���ꂪ���V�ɑ�������B
|
�@���T�ƕ��ʁE�G�߁E���x�@���āA���T�̐��藧���ɂ��Ă͂��̂��炢�ɂ��āA��������͊e�T�ɔz����鎖�ۂ��������E���Ă݂悤�B�Ղ����̐��̒��̂��ׂĂ�����s�����Ƃ����̂��A���ɂ��̔��T�̑��`���ɂ��̂��B�����Ƃ��A���̐��̒��̑S�W�����������̂����T�Ȃ̂�����A���`�œ��R�Ȃ̂����E�E�E�B �@���T�@�@�@ ���ʁ@�G�߁@�܍s�@�\���@�\��x �@☰���i�V�j�@���k�@�@�@�@���@�@�@�@�@���� �@☱�[�i��j�@���@�@�H�@�@���@�@�M�h�@�� �@☲���i�j�@��@�@�ā@�@�@�@�����@�� �@☳�k�i���j�@���@�@�t�@�@�@�@�b���@�K �@☴�F�i���j�@����@�@�@�@�@�@�@�@�@�C�� �@☵���i���j�@�k�@�@�~�@�@���@�@�pᡁ@�q �@☶���i�R�j�@���k�@�@�@�@�y�@�@��@�@�N�� �@☷���i�n�j�@����@�@�@�@�y�@�@�ȁ@�@���\ ���������\���̂����̕�ƌȂ́A ����̌T�ɂ��z���Ȃ��A�Ƃ����������B �����}�ɂ���Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
�@���X�A�����F�Ə����āu�C���v�ƌP�܂�����A���k�����Ə����āu����v�ƌP�܂���n����l���ɏo����Ƃ����邪�A����ȂƂ��ɂ͈Ղ����������̋�C���������āA�������������悤�Ȋ������悤�ȁA����ȋC���ɂ��Ȃ�͎̂��������낤���c�B |
�@���T�Ɛl���@�l�̂ł́A���̂悤�ɔz����B �@☰���i�V�j���V�͍ł���ɂ���B�@ �@☱�[�i��j���������͊��ŏ��B �@☲���i�j��ځ��͖��炩�ɏƂ炵�A�ڂ͖��炩�ɂ��̂�����߂�B �@☳�k�i���j�𑫁��l�͑������Ĉړ�����B �@☴�F�i���j���ҁ��҂͑��ɏ]���ē����B �@☵���i���j�������ׂ�Ƃ���͌��A�l�̂̌��ƌ����Ύ��A�܂����̌T���c�ɂ���ƍ��E�Ɍ�������l�q���ے�����}�`�ɂ������A���͊�̍��E�ɂ��錊�ł�����B �@☶���i�R�j����܂��͔w����͂��̂��x���~�߂�B�܂��A�~�߂�Ƃ����Ӗ�����A�l�̂ň�ԓ������Ȃ��A�~�܂��Ă��鏊�Ƃ��Ĕw�Ƃ�����B �@☷���i�n�j����n�͖����𑠂߁A���͐H�ׂ����̂𑠂߂�Ƃ���B �@���̂ق��ɂ��A�w�Ռo�x�́u���T�`�v�Ƃ����Ƃ���ŁA���T�ɂ͐F�X�Ȏ��ۂ��z����Ă��邱�Ƃ�������Ă���̂����A���̗l�q�͊e�T�ʂɂ܂Ƃ߂Ă����B �@���T���������ۂƂ��̍����@☰���i�V�j�͓V���ō����ł��邱�Ƃ���A�l�̏�ɗ��N���鉤�A��ЂŌ����ΎВ��Ƃ������ō����͎ҁB�z�̋ɂ݂ł��邱�Ƃ���\���Ƃ��āA�V�n�̊Ԃ��c�����s�ɍs�������闳�A�l���\���������߂ɏ�铮���̔n�B�z���������Ӗ����邱�Ƃ���A�������ł�������A�A���i��j�A�X�B�F�ł͍ł��ʓx�������ԁB�z�C�Ƃ��āA���C���������Ă���̎��i�̎��ɂ͎�q���Ȃ킿�V���������̑f�������Ă���j�B �@☱�[�i��j�́u��낱�ԁv�Ƃ������Ƃ���A�����ł͊��Ől�ɓ���r�B���A�̐^�̐�ڂ��E�݂ƃC���[�W����A�E�݂ɂ͐������܂邩��A���������̃R�b�v��e�B�e�͌v�ʂ��铹��ł����邱�Ƃ���u�v��v�Ƃ����s�ׁB�v��Ε����Ĕ����ł��邩�番���A�����A���i�B�R������悤�ɗ����J�B�����܂�ɂ͊炪�ʂ�̂ŁA�ʂ�Ƃ������Ƃ��狾�B�E�݂ɂ��Ȃ݁A�݂𝑂��P�B�ŏ�̈�A���q�r���������l�q�Ƃ��āA�������Ƀq�r����������ԁB���ꂽ��ɂ悭������q�r���ꂽ�����y�B �@☲���i�j�͉ɂ��Ȃݖ��邳�������炷���i���z�j�B�t������Ƃ������Ƃ���A�g�ɒ����鑕���i��b�h�B�����ł͏_��Ȑg�������k�Ŏ��I�A�ځA�T�A�L�ȂǁB�܂��A�㉺�̃j�z�𗃂Ƃ��Ē��A���ł��������H�Őg����賁B �@☳�k�i���j�͗��ɂ��Ȃ݉��B�A���ł͈�z��߁A�j�A��߂Ɛ߂̊Ԃ̕����Ƃ��Ē|�A���A���A��A�B�Ƃ������߂̂���C�l�Ȃ̗��i�k���d�Ȃ�悤�ɐ�������j��A���莞�ɔ����ƂȂ铡�A���A�哤�Ƃ������}���Ȃ���і��̗��i�����Ƃ́A�܂�������ɐL���A�n�\�Ɏ��钼�O�Ŕ��]���Ēn���ɖ߂�A���̌�A�肪���������グ�悤�Ƃ��Ă����Ԃ̂��ƂŁA���ꂪ���̌T�̃C���[�W�Əd�Ȃ�̂��j�A����z���ォ��~���ė����A�̏����ȕ���}���Ă���Ƃ��ĉ����B �@☴�F�i���j�͕����^�Ԃ��̂Ƃ��ĉ_��L���B�@����o���肷�镗�Ƃ��đ��B���ɏ���ċ���s���Ƃ��납�璹�B�܂��t�ɁA�j�z�̓V��̉��Ɉ�A����������Ă���Ƃ��납��A�n��ɕ����Ĕ�ׂ��A�l�ɂ悭���]���{�B�����r���n�ɕ����Ƃ��납�瑐�B�j�z�͂��̐��Ƃ��ď��A��A�͉���̂ŁA�㉺�ɐL������l�q�Ƃ��āu�����v�B���ɉA�Ȃ鍪��A��ɗz�Ȃ銲��L���A�͍����Ȃ邱�Ƃ���u�����v�B�����^�ԉ_�̐F�Ƃ��Ĕ��B �@☵���i���j�́u�ׂ�v�Ƃ������Ƃ��猯��B����̐��ł���ŁB�������ΔY�ނ̂ŗJ����S�a�B�g�̂̒��𗬂��t�̂Ƃ��Č��B���C�̌�������B�����ɐ��ސ����B �@☶���i�R�j�́u�Ƃǂ߂�v�Ƃ������Ƃ���A�l�̏o������~�߂��ˁB�O�G��h���~�߂邽�߂ɒz����B�܂��R�͐_��ł��邱�Ƃ���_���J��{�B�R���̏ے��ł����B��z���ŏ�ʂɓo��l�߂��`������u�o��v�Ƃ��������B�R�ɐ��ޓ����Ƃ��ČF�⎭�B�O�G��h���~�߁A�l����铮���Ƃ��ċ�i���j�B �@☷���i�n�j�͑�n�ł��邱�Ƃ��畽��A���B�H���Y����c���B�����ł͏_���ȋ��B�܂��A���̌T�̌����ڂ̌`���ׂ������R�Ƃ��Ă��邱�Ƃ���A�͗l�Ƃ��ĕ��B �@���T�ɔz����鎖�ۂ͑��ɂ����������邪�A�������e�ׂɎ��グ�Ă��肪�Ȃ��̂ŁA����͂��̕ӂɂ��Ă������B |
�ŏI�X�V���F�ߘa07�N11��09�� �w�L�u��
Copyright Heisei12th�`Reiwa7th�i2660�`2685�j�@�iC�j2000�`2025 GakuEki-UQkai
���T�C�g�̓��e�͂��ׂĖ��f�]�ڂ��֎~���܂�